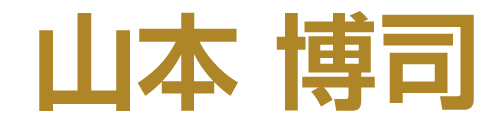未分類
東洋のマチュピチュ・天空の産業遺跡に感動(愛媛県新居浜市)
「東洋のマチュピチュ」と言われているマイントピア別子・東平(とうなる)ゾーンを視察。 標高750mの山中にある東平は、大正5年から昭和5年までの間、別子鉱山の採鉱本部が置かれ、社宅・小学校・劇場・接待館が建てられるなど、 […]
天然ヒノキで癒しの積み木を多くの人に!(愛媛県新居浜市)
早朝7時25分の飛行機で松山空港へ向かう。松山に着くと大雨。車で新居浜市へ。 地元真鍋光新居浜市議と共に、積み木作家で活躍する御子柴真由美さんを新居浜市内の作業所でお会いし、懇談。ヒノキの自然な積み木の魅力と活動の様子を […]
目黒区支部会で国政報告 (東京都)
午前中、社会保障トータルビジョン検討会の各部門で勉強会。 夕方から全体会議。「貧困と格差について」説明。 「雇用」など活発な意見交換が行われた。 夜、目黒総支部関グループの支部会に参加。 関けんいち区議から区政報告・党員 […]
..高齢者や障がい者出所後の支援探る/刑務所、社会復帰施設を視察/栃木県で浜田、山本(博)氏
<これまでの活動記録> 浜田昌良参院法務委員長(公明党)と、公明党の山本博司参院議員は21日、栃木県大田原市にある黒羽刑務所を訪れ、受刑者への対応状況など法務行政の課題を探った。 黒羽刑務所には、1472人の受刑者を収 […]
受刑者社会復帰支援へ!黒羽刑務所・喜連川社会復帰促進センター視察(栃木県大田原市・さくら市)
朝、東京駅から東北新幹線なすの号で那須塩原駅へ。 栃木県大田原市にある黒羽刑務所(くろばね)を浜田参議院法務委員長と視察。 小林所長・小山総務部長などから概要の説明を聞き、視察内を見学する。 収容定員1820名で実際は1 […]
地域貢献に取組むはちきん女性のパワーに脱帽! (高知県須崎市)
午後から須崎市内を佐々木学市議と地元企業や団体など訪問。 地元の林業・商店街など懸命に取組む皆様から課題・要望を伺う。 須崎市にある創業116年の竹虎(株)山岸竹材店を訪問。全国唯一の虎斑竹(とらふだけ)を扱う竹材専業メ […]
須崎市佐々木まなぶ市議と共に3箇所での街頭演説(高知県須崎市)
本日は1日高知県須崎市(すさき)を地元佐々木学(まなぶ)市議とまわる。 須崎市は高知県の中部に位置し、太平洋に面する市。市内を流れる新荘川にはニホンカワウソが生息している痕跡が近年まで報告されている。 人口24,822人 […]
『400年の歴史・小豆島石のシンポジウム』(香川県小豆郡土庄町)
『小豆島石のシンポジウム』が土庄町立中央公民館で開催し、大勢の皆様が参加。 小豆島は良質な花崗岩が採れる事で知られ、過去には大阪城の石垣へも小豆島の石がたくさん切り出されている。島の繁栄を支えた石材産業の歴史や文化的な価 […]
20世紀を代表する彫刻家「イサム・ノグチ庭園美術館」見学(香川県高松市)
香川県高松市牟礼町にあるイサム・ノグチ庭園美術館を初めて見学。イサム・ノグチの表現されている世界に大変感動した。 彫刻家、イサム・ノグチの150点あまりの彫刻作品はもとより、自ら選んで移築した展示蔵や住居イサム家、デザイ […]
LD支援 当事者の視点で/デジタル教科書 普及推進へ意見交換/山本(博)、山本(香)氏
<これまでの活動記録> 公明党障がい者福祉委員会の山本博司事務局長(参院議員)と山本香苗参院議員は17日、東京都目黒区の東京大学先端科学技術研究センターを訪れ、読み書きに困難を伴う学習障がい(LD)のある児童・生徒の学 […]
「貧困と格差」克服へ!「ナショナルミニマム研究会」中間報告(東京都)
午後から厚生労働部会(渡辺部会長)が開催。 「ナショナルミニマム研究会」の中間報告・「貧困と格差」問題に関する平成23年度概算要求について厚生労働省よりヒアリングし、意見交換を進めた。 「社会保障トータルビジョン検討会」 […]
読み書き困難な児童を救え!東大先端研の実演に感銘(東京都)
午前中、山本かなえ参議院議員と共に、障がい者福祉委員会として東京大学先端科学技術研究センターを視察。発達障がい児に多い、読み書き困難な児童への支援機器(デジタル教科書など)について中邑教授・河野準教授・巖淵准教授の3人の […]
ボランティアの力に感銘/創立70周年 日本点字図書館を視察/山口代表ら
<これまでの活動記録> 公明党の山口那津男代表は16日、東京都新宿区の社会福祉法人・日本点字図書館(田中徹二理事長)を訪れ、創立70周年を迎えた同館の取り組みを視察するとともに、情報化時代における視覚障がい者の支援策に […]
被害者切り捨て許せぬ/B型肝炎訴訟 原告ら公明に訴え
<これまでの活動記録> 公明党の肝炎対策プロジェクトチーム(PT、赤松正雄座長=衆院議員)は16日、衆院第2議員会館で全国B型肝炎訴訟の原告団、弁護団から、同訴訟の早期和解に向けた協力を要請された。坂口力副代表らが出席 […]