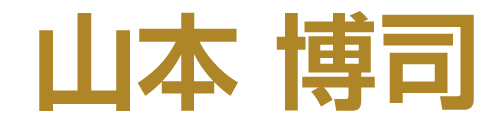手話の普及へ「推進法」実現
手話の普及へ「推進法」実現 喜怒哀楽伝える大切な言語/習得の環境整備など国・自治体の責務明記
「手話は私たちの大切な言語」と、当事者らが10年以上にわたり訴え続けてきた運動が、「手話施策推進法」という形で先の通常国会において結実した。超党派による議員立法で、手話に関する法制定は初めて。同法を紹介し、全日本ろうあ連盟の久松三二事務局長に成立の経緯を聞いた。
きこえない・きこえにくいため日常的に手話を使う「ろう者」は、国内に少なくとも5万~6万人いるとされる。
当事者にとって手話は「喜怒哀楽を自由にコミュニケーションでき、生きることそのもの」(久松事務局長)だ。2006年の国連総会で採択された障害者権利条約で、手話は言語の一つだと定義されている。
国内でも、11年に改正された障害者基本法において、手話は言語であることが明記されたが、具体的な環境整備のための法律がなかった。そのため、全日本ろうあ連盟など当事者らは法制定を求める運動を続けてきた。
■ようやく、ここまで
「ようやく、ここまでこぎ着けた。公明党には感謝しかない」。6月18日に手話施策推進法が衆院本会議で全会一致で可決、成立するのを見届けた全日本ろうあ連盟の石橋大吾理事長は、国会内で公明党の斉藤鉄夫代表らと面会し、こう喜びを語った。
同法では、手話の普及に向けた施策の策定・実施を国や自治体の責務と明記。習得や使用に関する合理的配慮が行われる環境整備、手話文化の保存や継承、発展が盛り込まれ、施策に必要な財政措置を国に義務付けた。
学校教育に関しては、児童生徒が手話で教育を受けられるよう手話技能を持つ教員や通訳者の配置を進めるとした。さらに「手話言語の国際デー」である9月23日を「手話の日」と定めており、6月25日から施行されている。
■合意形成に奔走
公明党は当事者の切実な思いを受け止め、国と地方で同法制定に尽力してきた。
13年に鳥取県で全国初となる手話言語条例の成立を推進。以降、各地の地方議会で同条例の制定や、「手話言語法」を求める国への意見書の採択を後押ししてきた。
国においては「電話リレーサービス法」(20年成立)や「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」(22年成立)の整備を進め、手話施策推進法においても、超党派議連で幹事長を務める山本博司参院議員が与野党間の合意形成に奔走し、今国会での成立に尽力した。
■全地方議会で意見書採択。公明の支援が大きな力に/全日本ろうあ連盟 久松三二事務局長に聞く
――法制化を求めてきた背景は。
ろう学校では長い間、口の動きを読んで会話する「口話教育」の邪魔になるとして、手話を使う子どもは叱られたり、体罰を受けるような時代があった。
また、社会は私たちを障がい者と位置付けるが、手話が通じる世界では何も不自由はない。「障壁」をつくり出しているのは、むしろ社会の方だと考えている。
そのため、私たちは国に手話を言語として認め、必要な施策を求める運動を続けてきた。
――成立の経緯は。
当初、手話が日本語と違った文法体系がある独自の言語であることに、理解が得られなかった。
そこで私たちは、まずはそれぞれの地域で理解を広げようと、市民と共に地方議会に働き掛け、600以上の自治体で手話言語条例を作ることができた。
さらに各地方議会から国に対して、「手話言語法」制定を求める意見書を出してもらった。全国1788自治体の全ての議会で採択されており、これは議会史上、初めてではないか。そうした地域からの声が政治を動かし、法制定につながった。
公明党の地方議員は早くから私たちの運動に理解を示し、尽力いただいた。これが大きな力となった。国では、山本博司参院議員が私たちの窓口となり、与野党の橋渡し役を担ってくれた。大変感謝している。
――デジタルツールが普及する中、手話の必要性は変わらないか。
きこえる人が、うれしかったことや悲しかったことを親しい人に何でも話すように、私たちにとって内面も含めて自由に伝えられるのが手話だ。
もちろん文字でも意思疎通は可能だが、感情までは十分伝えられない。いくらデジタルツールが発達しても手話がなくなることはないと思う。
――今後に向けては。
今年11月、ろう者の国際スポーツ大会「デフリンピック」が日本で初めて開催される。海外から大勢のろう者が訪れ、各地で“手話の花”が咲くだろう。きこえる人にとっても、手話に関心を持ち、理解が広げるきっかけになればと願っている。
2025/07/25 公明新聞 3面