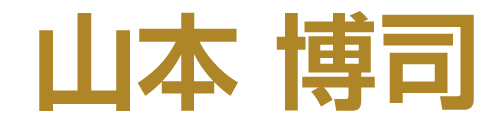支援法成立20年 発達障がい者の輝く社会へ
支援法成立20年 発達障がい者の輝く社会へ
乳幼児期から成年期まで、支える体制を切れ目なく
発達障がいのある人が能力aを発揮し、輝く社会へ――。先月で、超党派の議員立法による発達障害者支援法(以下、支援法)が成立して20年。乳幼児期から成年期までの切れ目ない支援体制づくりが着実に進んでいる。
■早期発見
支援法に基づき、発達障がい児・者とその家族を総合的に支援する地域拠点として、「発達障害者支援センター」が全国102カ所に整備されている。さらに乳幼児期の早期発見・支援に大きな役割を果たしているのが全国に1万2852カ所(昨年8月時点)ある児童発達支援センターと児童発達支援事業所だ。2010年の児童福祉法改正で発達障がい児も支援対象に加わっている。
例えば川崎市では、児童発達支援事業所の機能を持つ、子ども発達・相談センター「きっずサポート」を全7区に整備している。障がいの有無を問わず、発達に心配のある18歳未満の子と、その保護者が対象だ。市の担当者は「医療機関や従来の施設では何カ月も待たなければならないことが多かった。すぐに相談できる体制をつくったことで保護者の不安解消に役立っている」と語る。
■教育
教育現場では、発達障がい児の受け皿が広がっている。通常学級に在籍しながら障がいに応じた特別指導を別教室で受ける「通級指導」は、06年度から「学習障害」や「注意欠陥多動性障害」が対象に加わった。通級指導を担当する教員定数の改善や高校での通級指導の制度化が進んだ結果、この10年間で通級指導を受ける発達障がいの児童生徒数は4倍に増えている【グラフ参照】。
さらに、16年の支援法改正では、幼児期から一貫した教育的支援を、医療や福祉、労働などの関係機関と連携して行えるよう、個別の教育支援計画や指導計画を作成することが明記され、改訂された学習指導要領にも盛り込まれた。
■就労
発達障がい者が社会に出るタイミングでぶつかるのが就労の壁だが、支援法を受けて関連法が改正され、現在では幅広い就労支援を活用できるようになっている。
10年から知的障がいのない発達障がい者が精神障害者保健福祉手帳を取得できるようになり、18年から手帳を持つ発達障がい者も、民間企業や国・自治体に雇用義務が課されている障がい者雇用の対象となった。
全国のハローワークには発達障がいのある学生や求職者を支援するスタッフが配置されており、昨年度の発達障がい者の雇用者数は推計9万1000人(厚生労働省調べ)と、5年間で2・3倍伸びている。
■公明、立法・合意形成を主導
こうした切れ目なく支える体制づくりの原動力となった支援法の制定と改正を主導したのは公明党だ。04年1月、党内にワーキングチームを設置し、関係団体や識者との意見交換、視察活動を精力的に行った。同5月に超党派の議員連盟が発足した際には、公明党の福島豊衆院議員(当時)が事務局長を務め、法案成立に尽力した。
当時、厚労省で法案策定の実務を担った大塚晃氏(日本発達障害ネットワーク副理事長、元上智大学教授)は「福島議員が作成した原案がベースになった」と証言する。
16年の支援法改正においても、当時、超党派議連で事務局長を務めていた高木美智代衆院議員(現在は党アドバイザー)と山本博司参院議員が、立法作業や各会派との合意形成で中心的な役割を果たした。
<コメント>
■多様性をもっと認めて/日本発達障害ネットワーク理事長、児童精神科医 市川宏伸氏
支援法の制定時から公明党の国会議員が超党派議連の事務局長を務め、政党間の“接着剤”として合意形成を進めてくれている。地方議員も非常に熱心で、政党の中で公明党が一番、発達障がい者支援に力を入れてくれており、感謝している。
今後、最も必要なのは社会の価値観の転換だ。日本では発達障がいにネガティブなイメージを持っている人が多い。子どもの相談に訪れる親も、たいてい「うちの子は普通ですか」と言う。
しかし、米国であれば「なぜうちの子が、みんなと同じじゃないといけないのか」という考え方だ。米国のIT企業「アップル」を創業したスティーブ・ジョブズだって変わり者だった。日本も、そうした多様性をもっと認めていかなければ、世界からますます後れを取っていくだろう。
2025/01/10 公明新聞 3面